「公務員試験に合格するには予備校に通うべき?」
そう考える人は多いでしょう。ですが、実際には独学でも十分に合格可能です。
私自身、職業訓練校に通いながら、独学で公務員試験の勉強を進め、合格に達することができました。
この記事では、実体験をもとに「予備校に通わずに公務員試験を突破する勉強の進め方」を、筆記・小論文・面接の3ステップで具体的に解説します。
なぜ独学でも合格できるのか?
まず大前提として、公務員試験は「満点を取る必要のない試験」です。
資格試験のように満遍なく勉強する必要はありません。
筆記試験の目的は足切りラインを超えること。つまり、合格基準点(ボーダーライン)を超えれば良いのです。
たとえば特別区では、筆記試験の5割前後がとれれば、筆記試験に関しては合格ラインになると思います。ただ、その他にも専門試験や小論文試験も一定基準までできなければなりません。
筆記試験で満点を取得しても、小論文試験が白紙ならまず落ちます。平均的な点数を取る人が欲しいのです。
そのため、全科目を完璧に仕上げる必要はまったくないです。
限られた時間で効率よく点を取るには、頻出科目の重点学習と過去問演習、小論文課題の練習を徹底することが鍵になります。
筆記試験対策:出題頻度の高い科目を徹底的に
重点は「判断推理・空間把握・資料解釈・文章理解」
独学で最も力を入れるべきは、「数的処理」「判断推理」「文章理解」です。
この3つは配点が高く、出題率も安定しているため、得点源にしやすい分野です。
特に数的処理(判断推理・資料解釈)は、練習量が結果に直結します。
受験する自治体の過去問題集を繰り返し解くことで、問題パターンを体に覚え込ませましょう。
英語が苦手なら、文章理解の英語問題は思い切って捨ててもOKです。また分かったとしてもかなり時間がかかるなら捨てるのも戦略の一つです。
英語よりも現代文・資料解釈・数的処理の精度を上げる方が合格率は高まります。どの問題を正解しても点数は同じです。そうであれば、得点しやすい方に力を注いだ方が効率的です。
また英語は積み重ねの科目で、得手不手があります。公務員試験だけのために対策をするとなると非常に効率が悪いです。苦手ならバッサリ捨てて、資料解釈の精度をあげて、そこで着実に点数をとれるようにした方が良いです。資料解釈は時間をかければ、解けてくると考えています。
✅ ポイント
苦手科目を切り捨てて、得点しやすい分野に集中しましょう。
効率学習のコツ:過去問中心で“反復学習”
独学では、教材の取捨選択が命です。
いろんな参考書に手を出すのではなく、過去問1冊を繰り返す方が効果的。
- 受験する自治体の過去問10年分を目安に繰り返す。
- 『速攻の時事』:直前期に読むべき定番(これはやりましたが、効果があったか正直不明)。
最初は1問に30分かかっても構いません。
同じ問題を繰り返す。最初は分からなくても、そのうちパターンが分かってきますそして慣れることで正解までの時間が短くなります。
小論文対策:型を覚えれば怖くない
小論文は「書く力」ではなく「型の理解」が重要です。
独学でも十分対応可能で、特別な講座や添削サービスは不要です。
決められた時間に、決められた型で、小論文のルールで時間内に書くだけです。
独学での小論文勉強法
- 構成(型)を覚える
→ まずは「序論・本論・結論」の流れを理解。
『寺本康之の小論文バイブル』などが定番です(私はこれを使って練習しました)。 - 模範例を写す
→ いきなり書かずに、良い例文を何度か“書き写す”ことで構成を身体に覚えさせる。 - 時間を計って書く練習
→ 試験時間(60分など)を想定し、制限時間内で書く力を鍛える。また書かなくても、読んだ後に文章の内容を大まかに口頭で再現する(書くとなると時間がかかりますので、口頭で再現できればひとまずは大丈夫だと思います)。
💡 コツ:
小論文は「型どおりに整理された論理構成」が評価されます。
読みやすい文構成・正しい日本語・誤字脱字ゼロを意識しましょう。小論文の試験開始時にまず5分から10分かけて構成を考え、それから書きます。思いついたままに書くと構成が適当になります。
また練習していたものを一語一句再現しようとしないでください。それは無理ですし、応用が効かないです。おおよそ再現できれば大丈夫です。
【『寺本康之の小論文バイブル』はこちらでより詳細に紹介しています👇】

面接対策:お金をかけずにできる「実践トレーニング」
公務員試験の最終関門は面接。
予備校で面接講座を受けなくても、独学で十分対策可能です。
自宅でできる面接練習法
- 想定質問(志望動機・自己PR・長所短所・なぜ公務員か)をリスト化
- スマホで自分の話す姿を録音・撮影
- 鏡の前で繰り返し練習し、表情・姿勢・声のトーンを確認
面接は「会話のキャッチボール」ができれば十分です。
採用担当も人間なので、誠実さ・協調性・落ち着いた受け答えがあれば好印象を与えられます。
面接対策は一次試験の結果が分かってからやるとなると出遅れます。一次試験の間から毎日少しづつ準備をしておくことが大切です。
そうすれば、小論文で「あなたが理想とする公務員像に触れて論じなさい」と言われたときに対応することも出来ますし、小論文の「結論の締め」の部分でも書けます。面接対策以外にも役立ちます。
面接練習は、当然ですが、一人でやるより誰かと行った方が良いです。ただ一人でも大丈夫です。本番は緊張して上手く話せないかもしれませんが、日頃から練習しておけばある程度は対応できると思います。
✅ ポイント
面接の本番で緊張しないコツは「場数」。
模擬面接を録音して聞き返すだけでも、客観的に改善できます。面接対策は、できるだけ早めにとりかかる。
併願受験で“緊張を経験値に変える”
1つの自治体に絞るのではなく、複数受験をおすすめします。
1回目の面接で得た反省を、次回以降で改善できるため、結果的に経験値が積み上がります。
面接は回数を重ねるほど「慣れ」が成果に直結します。
当たり前ですが、いきなり本命の自治体は避けた方が良いです。精神衛生上も併願受験を勧めます。
独学合格を成功させる「3つの戦略」
勉強時間を“習慣化”する
社会人の場合、勉強は「時間」ではなく「習慣」で管理することが大切。
毎日1〜2時間、通勤や昼休みを使ってでも“机に向かうルーティン”をつくりましょう。スマホに小論文のPDFを入れて外出時でも読めるようにしたり、ボーっとしてる間に想定される質問や自己分析をしたり、少しの積み重ねを毎日した方が良いです。
休日に一気に詰め込むより、毎日コツコツ型が圧倒的に強いでし、効率的です。
情報収集はSNSや合格ブログを活用
最近はやYouTubeでも、独学合格者の体験談が多数公開されています。
勉強法・教材レビュー・モチベ維持法など、無料で質の高い情報が得られます。
試験制度の最新情報を必ず確認
自治体によっては、出題傾向や面接の方針、試験内容が変わる可能性もあるので、必ずチェックしておきましょう。
まとめ|予備校なしでも合格できる。必要なのは戦略と継続力
- 満点を取る必要はない。出題頻度の高い科目に集中。
- 小論文は「型」を覚え、書き写しと時間管理の練習で十分。
- 面接は「場数」と「客観視」。録音・併願で練習を重ねる。鏡をみて練習。
- 勉強を“習慣化”し、効率的に情報を取り入れる。
公務員試験は努力の方向を間違えなければ、独学でも十分に突破可能な試験です。
むしろ、コストを抑えつつ自分のペースで学べるのが最大のメリット。
30代からでも遅くありません。今日から一歩ずつ始めてみましょう。
▼ note / X(Twitter)でも発信しています
\ 学習・キャリア戦略の最新情報はこちらでも発信中 /
- note(ストーリー・キャリア戦略):けんしろう ❘ 凡人のキャリア再構築
→ 再スタートを切りたい人向けの深い内容、書き下ろしの体験談を更新中。 - X(Twitter):けんしろう|凡人のキャリア再構築
→ 公務員試験・資格勉強の「毎日の気づき・短文Tips」、キャリアの考え方を発信。
【公務員試験対策はこちら】
-

●公務員(社会人向け)通信講座比較― 独学が基本。でも「時間・戦略・安心」を買う選択肢もある ―
-


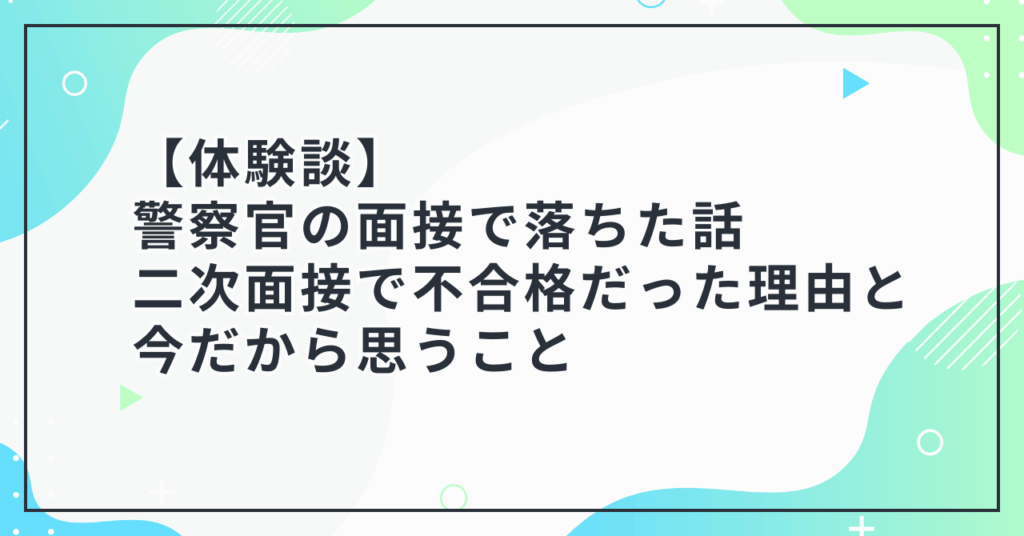
【体験談】警察官の面接で落ちた話|二次面接で不合格だった理由と、今だから思うこと
-


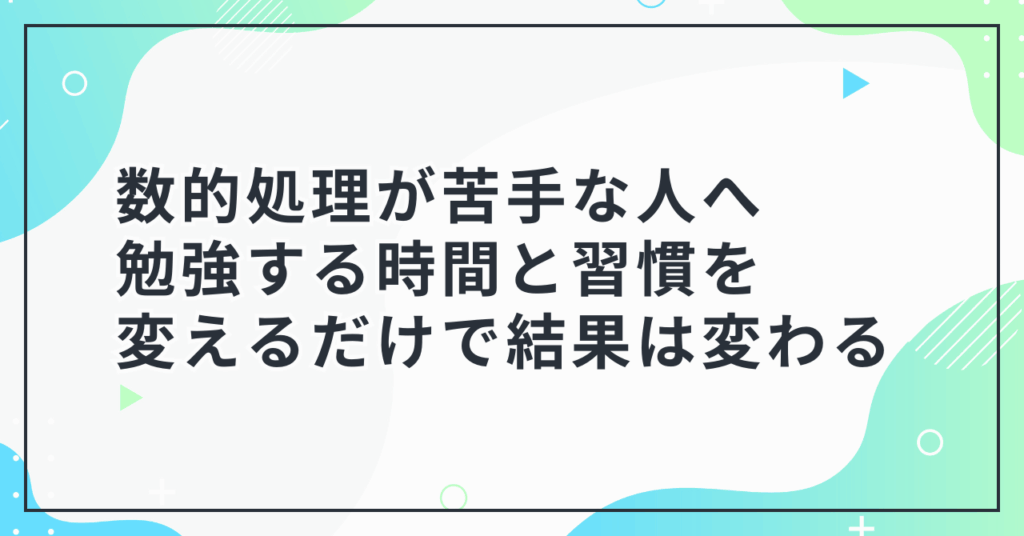
数的処理が苦手な人へ ― 勉強する時間と習慣を変えるだけで結果は変わる
-


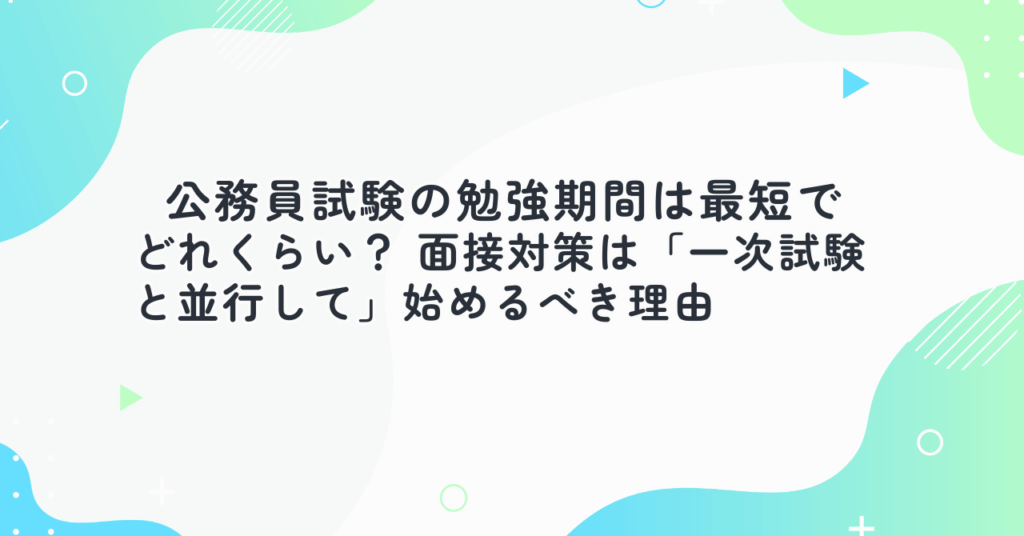
公務員試験の勉強期間は最短でどれくらい?面接対策は「一次試験と並行して」始めるべき理由
-


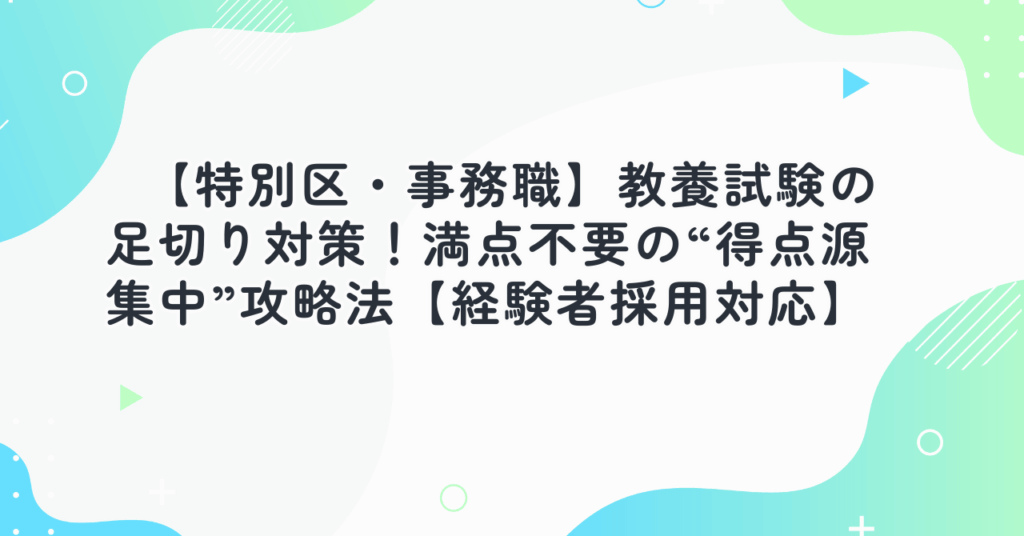
【特別区・事務職】教養試験の足切り対策!満点不要の“得点源集中”攻略法【経験者採用対応】
-


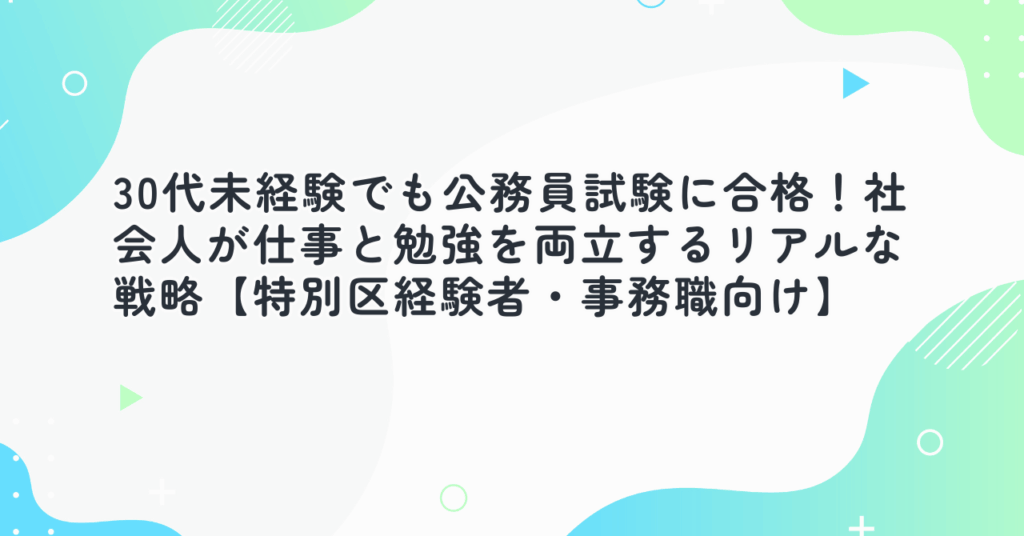
30代未経験でも公務員試験に合格!社会人が仕事と勉強を両立するリアルな戦略【特別区経験者・事務職向け】
-


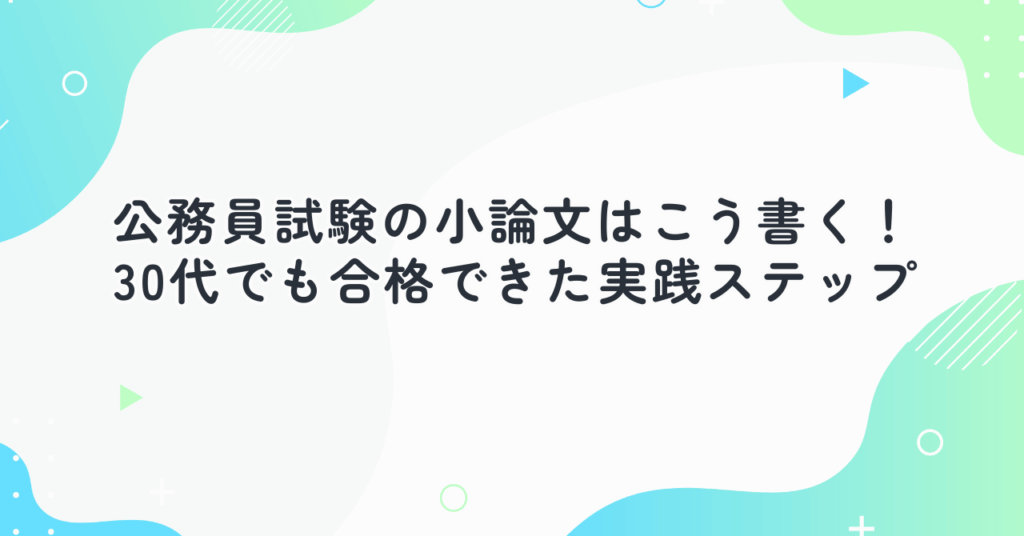
公務員試験の小論文はこう書く!30代でも合格できた実践ステップ
-


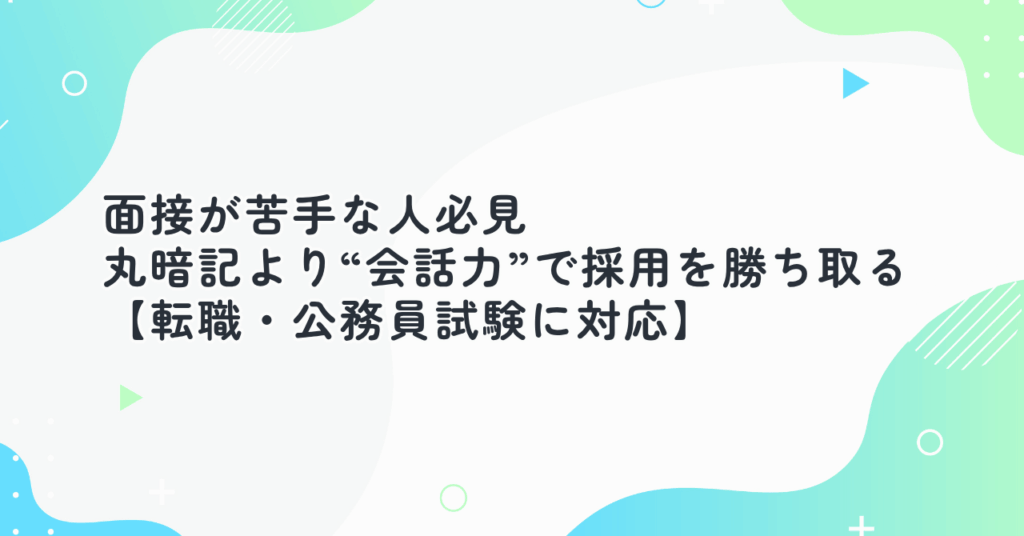
面接が苦手な人必見|丸暗記より“会話力”で採用を勝ち取る【転職・公務員試験に対応】
-


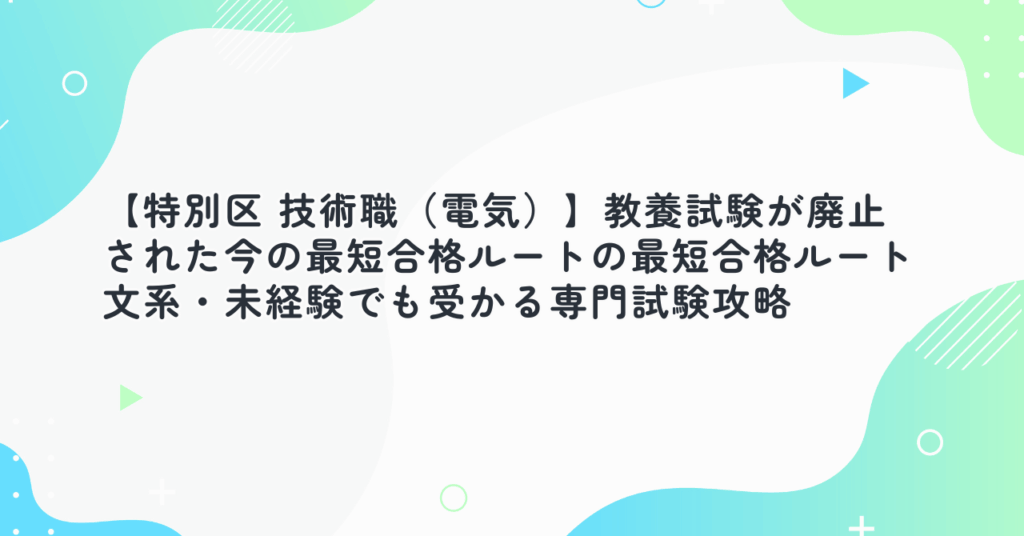
【特別区 技術職(電気)】教養試験が廃止された今の最短合格ルートの最短合格ルート|文系・未経験でも受かる専門試験攻略
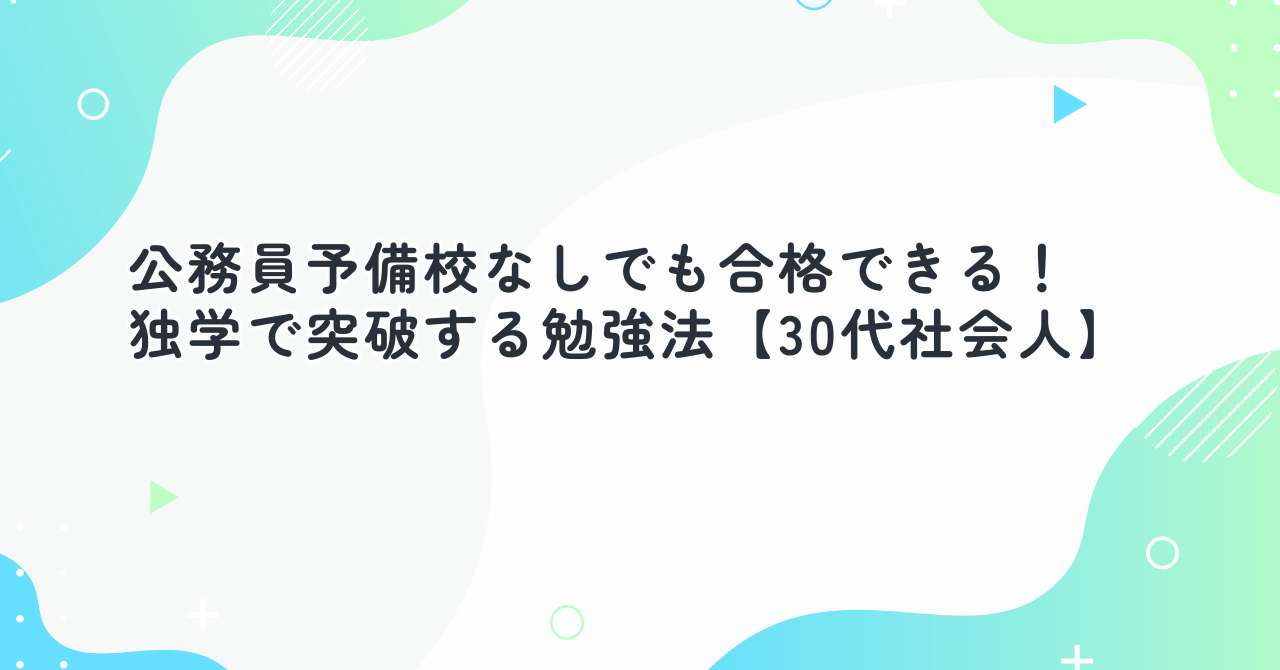
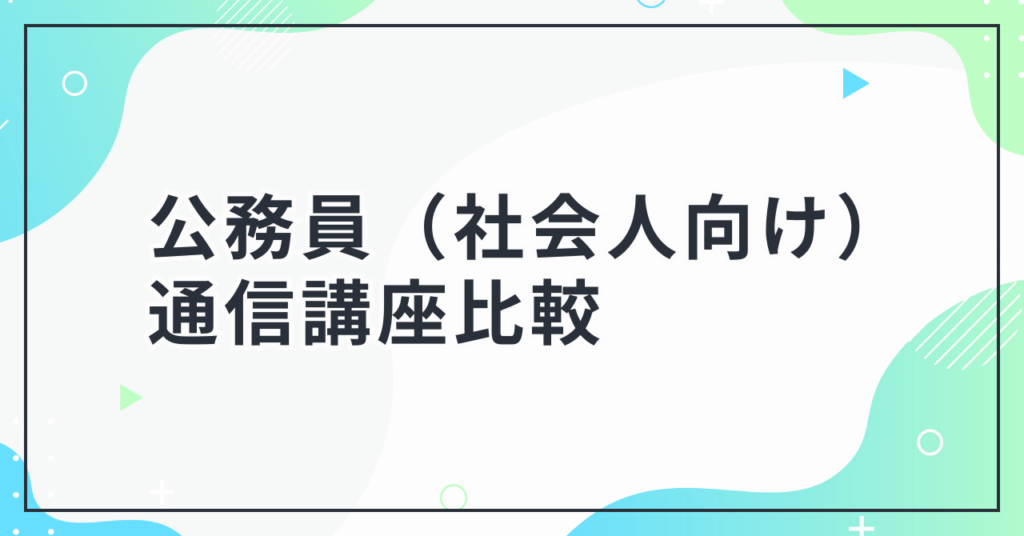
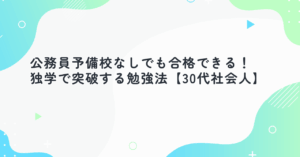

コメント