「30代からでも公務員になれるのか?」
「未経験で仕事を続けながら合格できるのか?」
そう悩んでいる社会人は多いはずです。私自身、30歳過ぎで民間企業から職業訓練校に入校しました。そこで公務員を受ける機会があり、目指しました。結果、職業訓練校に通いながら公務員や民間企業に採用されました。
この記事では、私の実体験をもとに、社会人でも無理なく合格を狙える勉強法とスケジュールを紹介します。時間がない社会人だからこそ、やるべきことを絞り、効率的に戦略を立てることがポイントです。
社会人は「週単位」で学習計画を立てる
まず最初に大切なのは、「勉強時間を確保できる仕組みを作ること」です。
社会人は平日にまとまった時間を取るのが難しいため、週単位での計画を立てるのがおすすめです。
私の場合、以下のようなスケジュールで勉強していました。
- 平日:1〜2時間(通勤+夜の時間)
- 休日:3〜4時間(午前+午後どちらか)
机に向かうだけが勉強ではありません。
通勤時間・昼休み・家事の合間などの「細切れの時間」を徹底的に活かすことが大切です。まとまった時間を捻出するよりも細切れの時間を捻出した方がトータルで多くなると思います。
平日で1~2時間、休日に3~4時間が多いように思えますが、細切れの時間を有効活用すれば、おそらくもっと時間を捻出できると思います。
一つひとつの細切れ時間がわずかでも、1日・1週間・1ヶ月単位で見ればかなりの時間になります。
特別区経験者試験で重点的に勉強すべき科目
特別区経験者(事務職・主事職)の場合、一次試験の足切りは教養試験です。
重点的に取り組むべき分野です。
- 数的処理(数的推理・判断推理・空間把握)
- 資料解釈(最重要)
- 文章理解(英語除く)
- 時事問題
上記が対策しやすい得点源です。特に資料解釈は時間をかければ点数がとれるといった特徴があります。
公務員試験では、出題傾向がパターン化されているため、過去問を繰り返し解くことで対応できます。同じ問題は出題されませんが、類似問題は出題されます。
また英語の長文問題が苦手な人は、思い切って“捨てる”のも戦略の一つ。
試験は「必須30問+選択5問」の全35問構成です。
そのうち18問前後の正解を目標にすれば筆記試験のボーダーラインには届きます(最低でも15問は正解したい)。
新卒向け試験に比べると問題は素直ですが、1問の重みが大きいので、
「広く浅く」よりも「狭く深く」「点数を着実に取れるところでとること」を意識して精度を高めることが重要です。
特に数的処理は、完璧を目指さなくてもOK。満点はおそらく無理です。
本番で5割取れれば十分です。
教養試験のボーダーラインを超えないと、小論文がよく書けたとしても読まれません。なので効率的に、最低ラインを超えるくらいまで対策が出来れば十分です。
小論文対策は「一次試験突破のカギ」
特別区経験者採用で重要なのが、小論文対策です。
教養試験だけでなく、小論文で合否が決まるケースが多いと思います。教養試験はボーダーラインさえ超えればそれ以上点数をとる意味はありません。
小論文は「課題論文」と「職務経験論文」の2種類がありますが、
まずは以下の3ステップを意識しましょう。
- 型(構成)を覚える:序論→本論→結論の流れをマスター
- 過去テーマを分析する:5〜6年分の出題傾向をチェック
- 10〜15本の想定されるテーマを事前に練習する
職務経験論文では、「これまでの経験をどう公務員として活かすか」を明確に書く必要があります。
これは面接でも問われる内容なので、自己分析を兼ねて書き出しておくと非常に効果的です。
また、小論文は「書く練習」だけでなく、「読む練習」も大切です。
完成した論文を何度も読み返し、試験時間内に書けるように体に覚えさせましょう(とにかく練習です)。
面接対策 ― 経験を“公務員らしく”語る準備を
一次試験を突破したら、次の大きな関門は面接です。
特に社会人受験者の場合、評価されるポイントは「過去の職務経験をどう活かせるか」。
面接でよく聞かれる質問は次の3つです。
- なぜ公務員を志望したのか
- 公務員である必要はあるのか
- なぜ民間から転職しようと思ったのか
- なぜその自治体を選んだのか
この4点は、具体例を交えて話せるように準備することが重要です。
抽象的な「社会に貢献したい」ではなく、
「公務員としてやりたいことをする上で、なぜ公務員である必要があるのか、前職や経験、自身の考えを踏まえ、具体的な表現亅をしないと説得力がありません。
また、特別区では「3分プレゼン」があります(新規採用ではありますが、経験者ではないかもしれません)。もし出題されたときに、練習していたいとまず答えることはできないので多少は頭に入れておいた方が良いかもしれません。
面接は緊張します。本番で緊張して話が飛ばないように、何度も録音して練習したり、鏡を見て練習したり、誰かと面接練習するのがおすすめです。面接は会話なので、経験者の方はないと思いますが、丸暗記は避けてください。
忙しい社会人ほど「効率化ツール」を活用すべき
社会人が合格するかどうかを分けるのは、勉強の量ではなく“効率”です。
私が実際に使って効果があったのは以下の2つのツールです。
- Studyplus(スタディプラス):勉強時間を記録・可視化できるアプリ
- Anki / Quizlet:暗記カードアプリ(通勤中に反復)
これらを使えば、「今日はどれだけ勉強したか」「何が弱点か」を数値で把握できます。
忙しい社会人ほど、アプリを活用して学習を“見える化”することが重要です。
また、スマホで「小論文の読み返し」や「時事問題の確認」もできるため、
紙の参考書に頼らず、どこでも勉強ができる環境を整えましょう。
正直、時事問題は対策しても難しいと思います。私は時事問題は半分とれれば良いと考えています。
社会人合格の本質は「広げない・絞る・継続する」
社会人が失敗しやすいのは、「全部をやろうとして続かない」ことです。
公務員試験は出題範囲が広いため、最初から完璧を目指すと必ず挫折します。
だからこそ、「やらないこと」を決める勇気が必要です。
特別区試験であれば、英語を捨ててその他の文章理解問題に集中するのも戦略の一つ。
また、数的処理で満点を狙うよりも「6割確保」を目標に、残りを文章理解で稼ぐ方が効率的です(全体で5割とれれば十分です)。
さらに、小論文や面接の準備は「早めに始める」のがポイント。
特に面接対策は一次試験の合否がでてからでは間に合わないため、筆記と並行して準備しておきましょう。
まとめ:30代・未経験でも合格できるのは「戦略的に動く人」
30代・未経験であっても、公務員試験は十分に合格可能です(30代とは書いていますが、40代でも十分に合格可能です)。
ポイントは「時間の使い方」と「勉強の取捨選択」。
平日は1〜2時間、休日は3〜4時間を確保し、
小論文と面接対策を早めに始める。
この2つを徹底するだけで、結果は大きく変わります。
私自身も社会人として忙しい中、「限られた時間で何をすべきか」を常に考えながら行動したことで、無理なく合格できました。
もし今、「もう30代だから遅いかも」と感じているなら、それは間違いです。
むしろ社会人経験を持つあなたこそが、公務員試験に向いています。
一見大変そうですが、公務員試験は資格の勉強よりもコスパは良いです。社会人採用であれば、職歴加算もされますし、中小・零細企業で働いている場合、おそらく給与は上がると思います。
▼ note / X(Twitter)でも発信しています
\ 学習・キャリア戦略の最新情報はこちらでも発信中 /
- note(ストーリー・キャリア戦略):けんしろう ❘ 凡人のキャリア再構築
→ 再スタートを切りたい人向けの深い内容、書き下ろしの体験談を更新中。 - X(Twitter):けんしろう|凡人のキャリア再構築
→ 公務員試験・資格勉強の「毎日の気づき・短文Tips」、キャリアの考え方を発信。
-

●公務員(社会人向け)通信講座比較― 独学が基本。でも「時間・戦略・安心」を買う選択肢もある ―
-


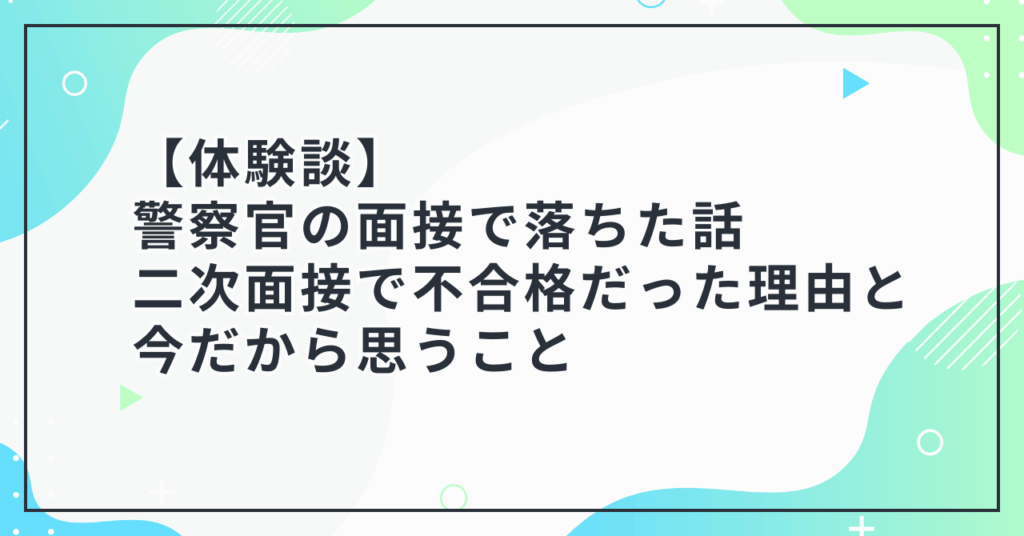
【体験談】警察官の面接で落ちた話|二次面接で不合格だった理由と、今だから思うこと
-


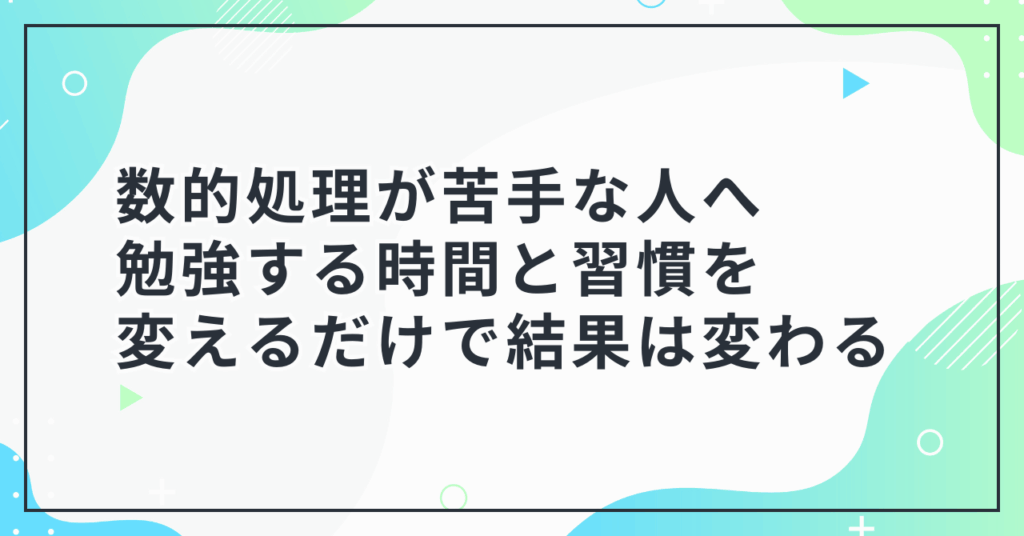
数的処理が苦手な人へ ― 勉強する時間と習慣を変えるだけで結果は変わる
-


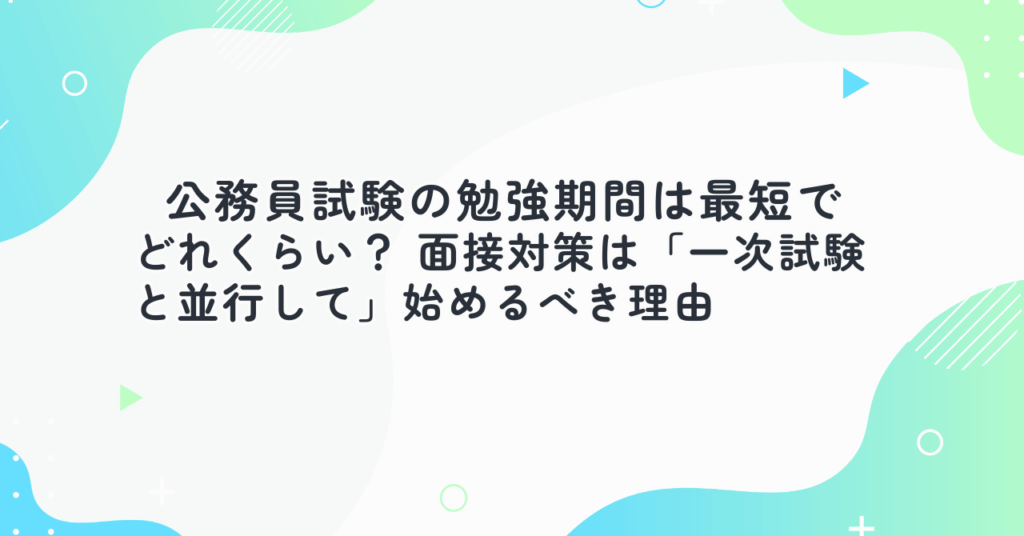
公務員試験の勉強期間は最短でどれくらい?面接対策は「一次試験と並行して」始めるべき理由
-


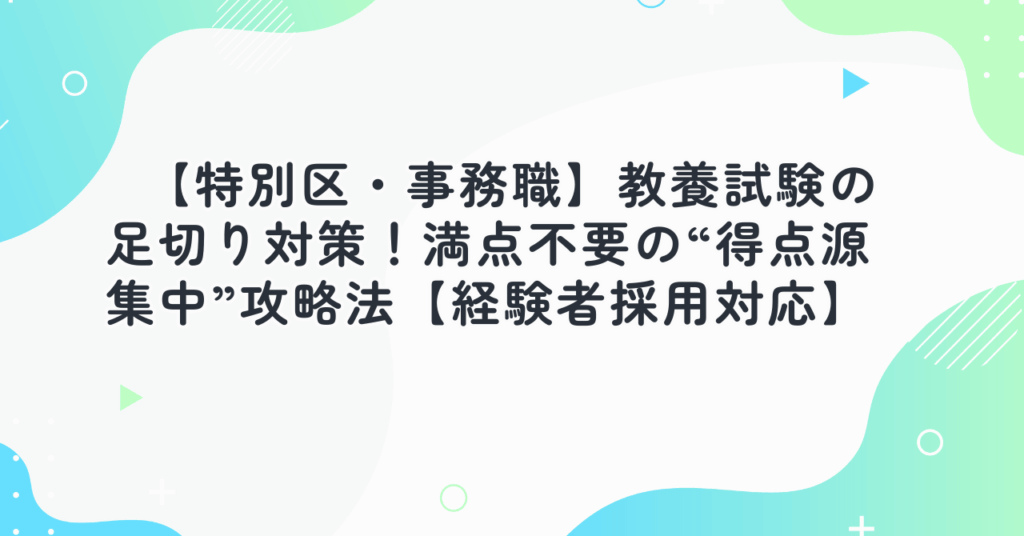
【特別区・事務職】教養試験の足切り対策!満点不要の“得点源集中”攻略法【経験者採用対応】
-


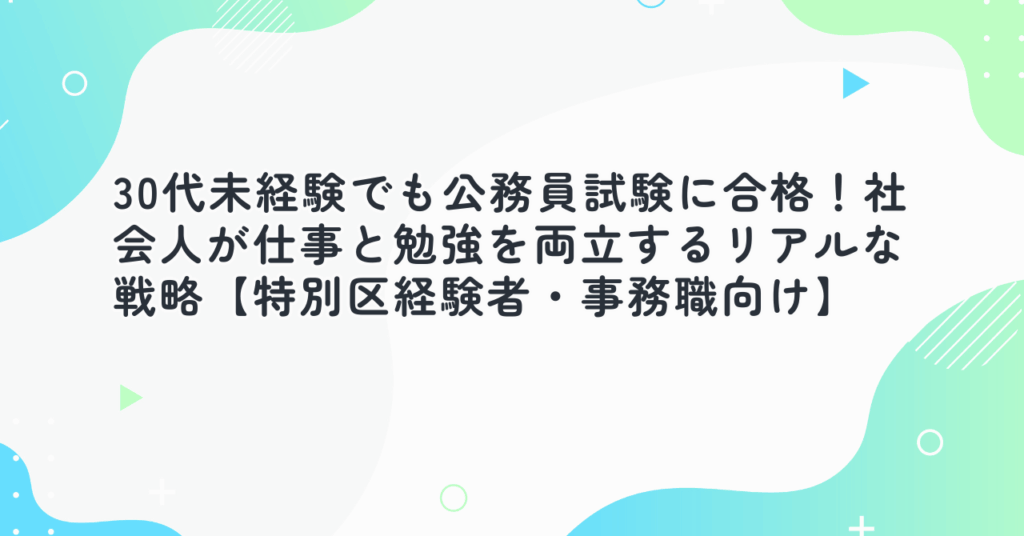
30代未経験でも公務員試験に合格!社会人が仕事と勉強を両立するリアルな戦略【特別区経験者・事務職向け】
-


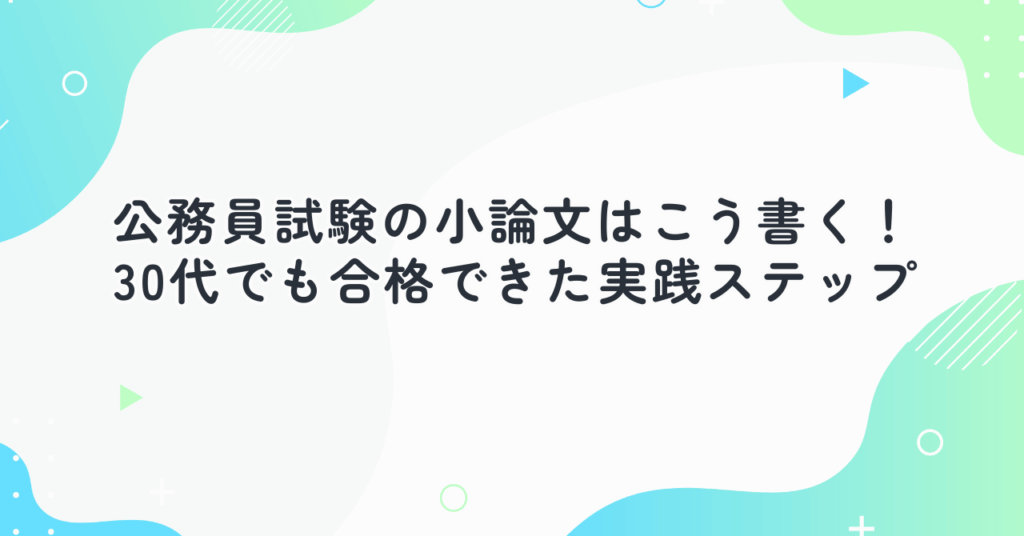
公務員試験の小論文はこう書く!30代でも合格できた実践ステップ
-


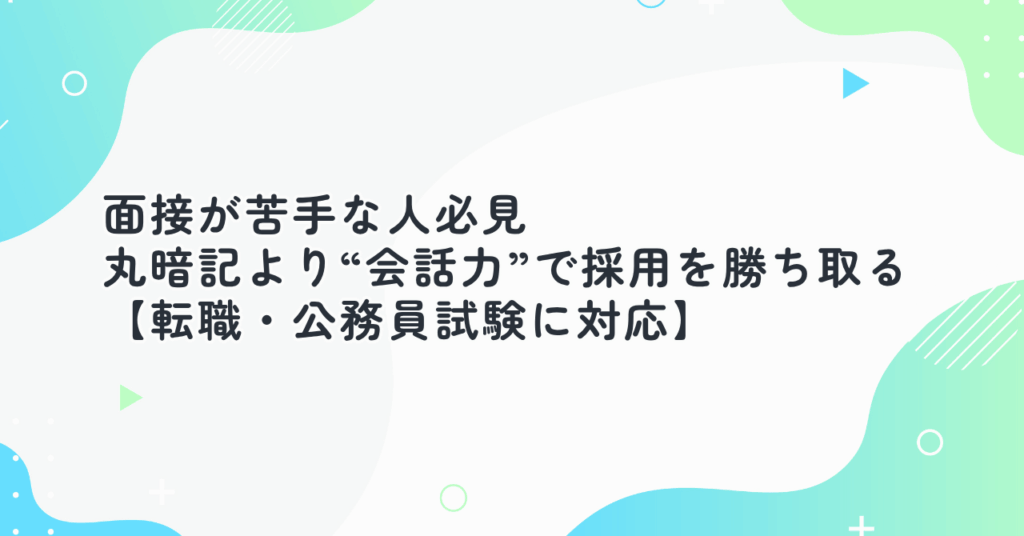
面接が苦手な人必見|丸暗記より“会話力”で採用を勝ち取る【転職・公務員試験に対応】
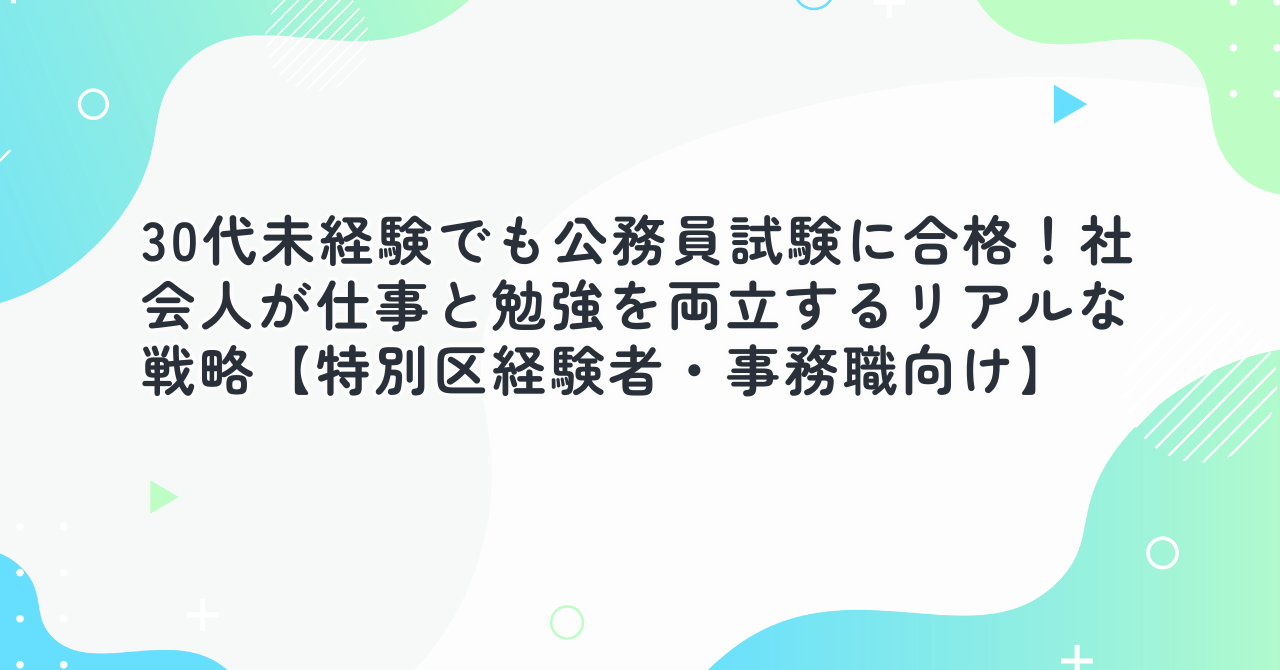
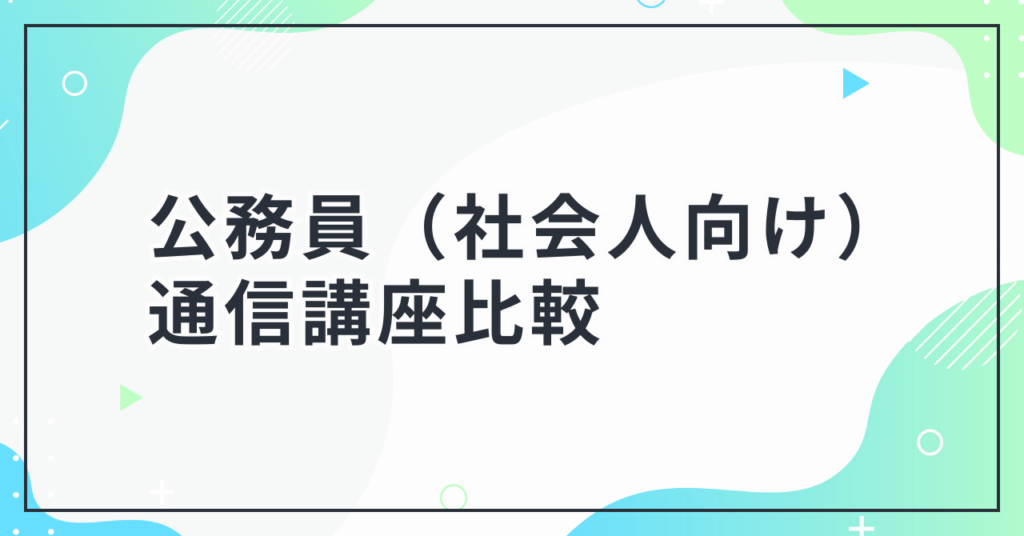
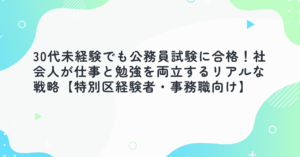

コメント