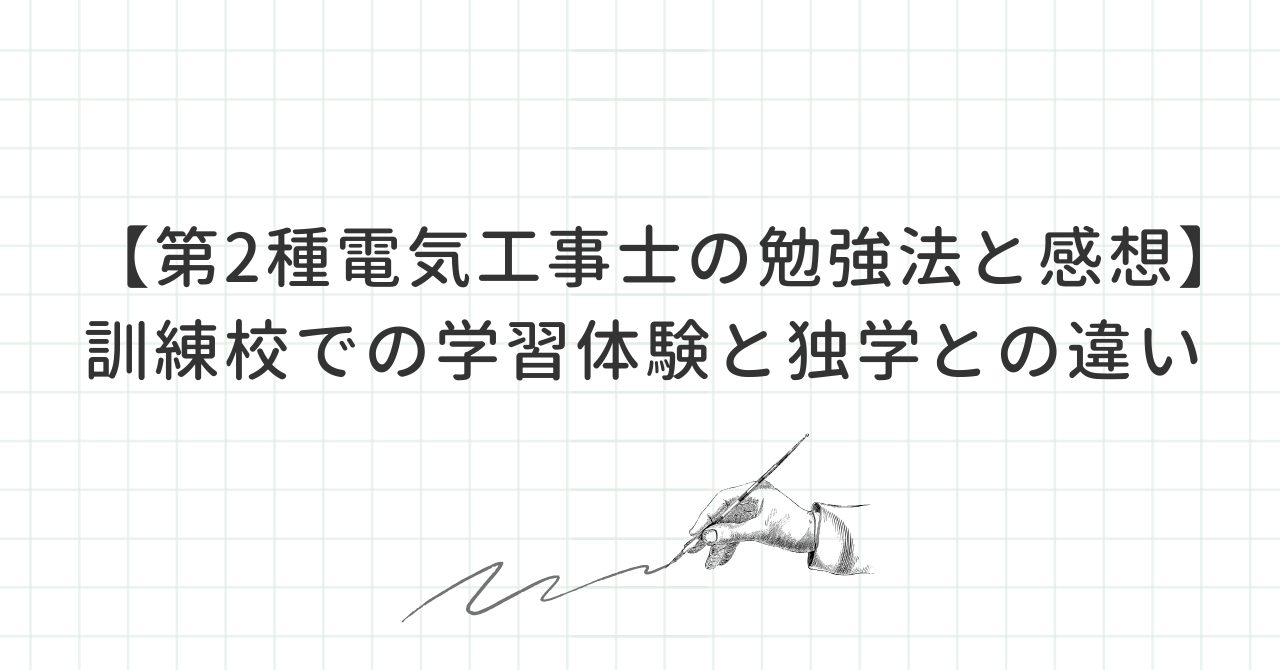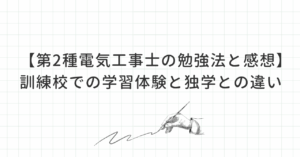Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
私が第2種電気工事士の資格を取得したのは、職業訓練校に通っていたときです。
当時は電気の知識がほとんどなく、工具の名前も分からない完全な初心者でした。
電気工事士の試験は年に2回(上期・下期)実施されるため、入校からすぐに試験対策が始まりました。やったことのない事を始めるので少なからず毎日緊張していました。
ですが、訓練校という環境で体系的に学べたおかげで、筆記・実技試験ともに1回で合格できました。
この記事では、私が実際に行った筆記・実技試験の勉強法、そして訓練校で学んで感じた独学との違いを、リアルな体験を交えて紹介します。
【筆記試験対策】写真暗記+過去問反復が合格の近道
第2種電気工事士の筆記試験は、マークシート方式の4択問題。
出題範囲は広いですが、頻出テーマは限られています。
特に「配線器具」「工具」「施工図」「電気理論」の4つが重要で、
中でも写真問題(実物写真を見て名称を答える問題)は得点源にできます。知っているかどうかだけで点数がとれるので対策しやすいです。
使用した教材
私が実際に使用したのは以下の2冊です。
📘 『ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 学科試験 すぃ〜っと合格』(オーム社)
図解が多く、初学者には最強の1冊。
📘 『第2種電気工事士 学科試験 過去問題集』(電気書院)
解説が丁寧。
どちらも図解が多く、初心者でも理解しやすい構成です。
特に『ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 学科試験 すぃ〜っと合格』は、まさに初心者の味方。
写真・イラスト・図解が豊富で、「読んで覚える」ではなく「見て覚える」ことに特化しています。
たとえば、コンセント・スイッチ・ジョイントボックスといった器具類も、
写真を繰り返し見ていくうちに自然と記憶に残るようになります。一回で覚えるのは難しいのでひたすら繰り返しです。
私はスキマ時間にスマホで器具の写真を眺めて暗記していました。
【『第2種電気工事士 』で使用した教材に関してはこちらで紹介しています👇】

電気理論は「理解→過去問→復習」のサイクル
最初に苦労したのは電気理論(オームの法則・抵抗計算・電力量など)です。
公式を覚えても、問題文を読むと混乱してしまう……そんな状態でした。
しかし、焦らず以下のステップを繰り返すことで理解が定着しました👇
1️⃣ テキストで基礎理論を理解する
2️⃣ 過去問を解く
3️⃣ 間違えた問題をノートにまとめる
4️⃣ 翌日また同じ問題を解き直す
このサイクルを5回転以上繰り返した結果、
本番では9割程の点数を取ることができました。
ただここで点数がとれなくても他の部分で点数をカバーできれば合格はできます。
効率を上げるコツ:苦手分野の“絞り込み復習”
私は最初、過去問を全部解いて満足していましたが、
実はそれでは効率が悪いと気づきました。
途中からは、「間違えた問題だけを繰り返す」方法に変更。
不安な問題にはチェックマークを付けて、
3周目以降はそこだけを重点的に解くようにしました。
結果、学習時間を3分の1に減らしながらも、
得点率はむしろ向上しました。
【実技試験対策】訓練校の環境が最大の強み
第2種電気工事士のもう一つの関門が「実技(技能)試験」です。
試験では、制限時間40分の中で複線図を書き、配線を組み、
正確な施工と安全な仕上がりが求められます。
使用した教材と練習内容
訓練校では、以下の教材を使用しました。
📘『2025年版 第二種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答』
訓練校では、公表問題13問すべてを実際に制作し、
講師が毎回チェックしてくれます。
私の場合、訓練校で1つの課題を3回ずつ繰り返し、
配線の順序やスイッチ結線を体で覚えるまで練習することができました。
最初のうちは被覆を剥きすぎたり、圧着が甘かったりと失敗続きでしたが、
講師のアドバイスを受けるうちに着実に上達していきました。
【『2025年版 第二種電気工事士技能試験 公表問題の合格解答』に関してはこちらで紹介しています👇】

工具・材料の貸出があるのは大きなメリット
訓練校では、
ペンチ・ドライバー・ニッパー・ストリッパーなどの専用工具がすべて貸出制でした。
独学の場合、これらを自前で揃えると1〜2万円はかかります。
さらに練習用の配線材料(ケーブル・スイッチ・コンセントなど)も高価で、
試験前に「練習したくても材料費がもったいない」と感じる人も多いです。
訓練校では、材料を惜しまず何度も練習できたため、
実技に対する不安を完全に払拭できました。
第2種電気工事士の受験にかかった費用は「交通費・テキスト代・受験費用」だけです。道具や配線材料には一切かかりませんでした。
実技練習で身についた2つの力
1️⃣ 施工手順を整理する力
限られた時間内で効率的に組むための「段取り力」が身につく。
2️⃣ 本番に動じない集中力
何度も練習しているので、試験本番でも焦らず淡々と作業できる。
この2つは独学ではなかなか身につきません。何度も練習したことで身につけられました。
【独学との違い】「練習環境」と「指導」が合否を分ける
独学でももちろん合格は可能です。
実際にSNSでも、独学で合格した人の体験談は多く見かけます。
ただし、私の実感としては
訓練校と独学の差は“環境と指導”にあると思います。
独学の限界:自分のミスに気づけない
独学の場合、作業の正誤を判断するのは自分だけ。
配線を間違えても「これでいい」と思い込んでしまうことがあります。
一方、訓練校では講師が1つひとつのミスを指摘してくれるため、
早い段階で修正できるのが大きな違いです。
私も最初は「ねじの締め方が甘い」「絶縁被覆が短い」など、
自分では気づけなかった部分を何度も指摘されました。
その度に着実に合格に近づいているということを実感しました。
練習量の差も大きい
独学では材料費を節約しようと、
どうしても「練習回数を減らす」傾向があります。不安なまま受験はしたくないが、かといって材料費はかけたくない。
訓練校では材料が支給されるため、
1つの課題を何度も作り直せる。
その結果、手が勝手に動くレベルまで習熟できました。
この「圧倒的な練習量の差」こそが、
合格率の差になって表れると思います。
【まとめ】第2種電気工事士は訓練校での取得が圧倒的に効率的
第2種電気工事士は、いわゆるビルメン4点セット
(電工二種・ボイラー技士・危険物乙4・冷凍機械責任者)の中でも、
唯一「実技試験」があるため、難易度は最も高い資格だと思います。
ただし、職業訓練校という環境を活用すれば、
初心者でも短期間で合格を狙えます。
職業訓練校に通う以外にも、東京都の「在職者向け職業訓練(キャリアアップ講習)」を利用する方法があります。第2種電気工事士の学科・技能試験対策コースがあり、講師から直接指導を受けられるため、独学だけが不安な方や実技に慣れたい方におすすめです。受講料も比較的安く、仕事と両立しながら学びやすい点がメリットです。
検討する方はこちら👇
キャリアアップ講習 | TOKYOはたらくネット
合格のポイントまとめ
📘 筆記試験対策
- 写真問題で器具・工具を暗記
- 電気理論は「理解+過去問反復」
- 苦手分野だけを重点的に復習
🔧 実技試験対策
- 公表問題13問を繰り返し練習
- 講師フィードバックでミス修正
- 工具・材料は訓練校に頼って効率化
この2つを徹底すれば、
初回受験でも十分に一発合格を狙えます。
【『第2種電気工事士 』で使用した教材に関してはこちらで紹介しています👇】

【職業訓練校での電気工事士取得体験】
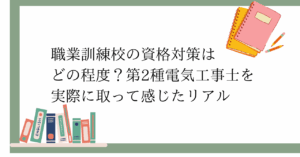
【電気工事士の勉強法・必要工具について解説】
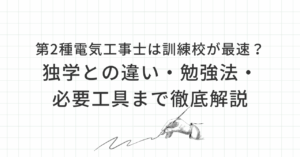
【2級ボイラー技士の受験を検討する方はこちら】
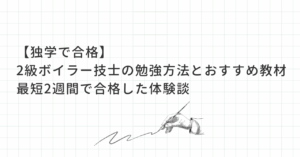

【ボイラー整備士の受験を検討する方はこちら】
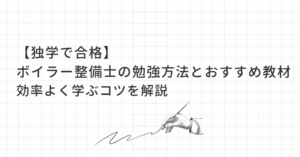
【危険物乙四の学習方法はこちら】
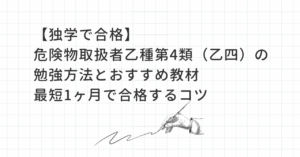
【資格勉強の始め方はこちらこちらを参照】
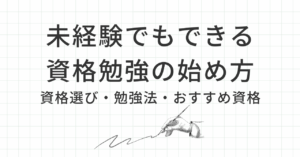
▼ note / X(Twitter)でも発信しています
\ 学習・キャリア戦略の最新情報はこちらでも発信中 /
X(Twitter):けんしろう|凡人のキャリア再構築
→ 公務員試験・資格勉強の「毎日の気づき・短文Tips」、キャリアの考え方を発信。
note(ストーリー・キャリア戦略):けんしろう ❘ 凡人のキャリア再構築
→ 再スタートを切りたい人向けの深い内容、書き下ろしの体験談を更新中。