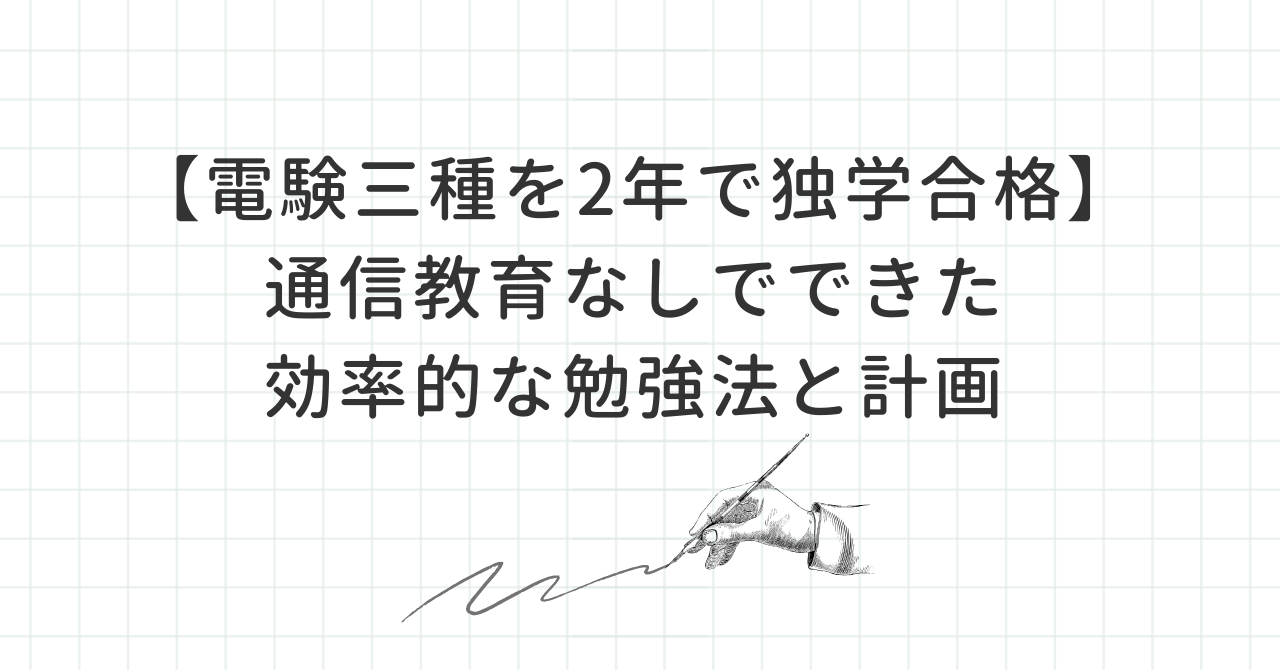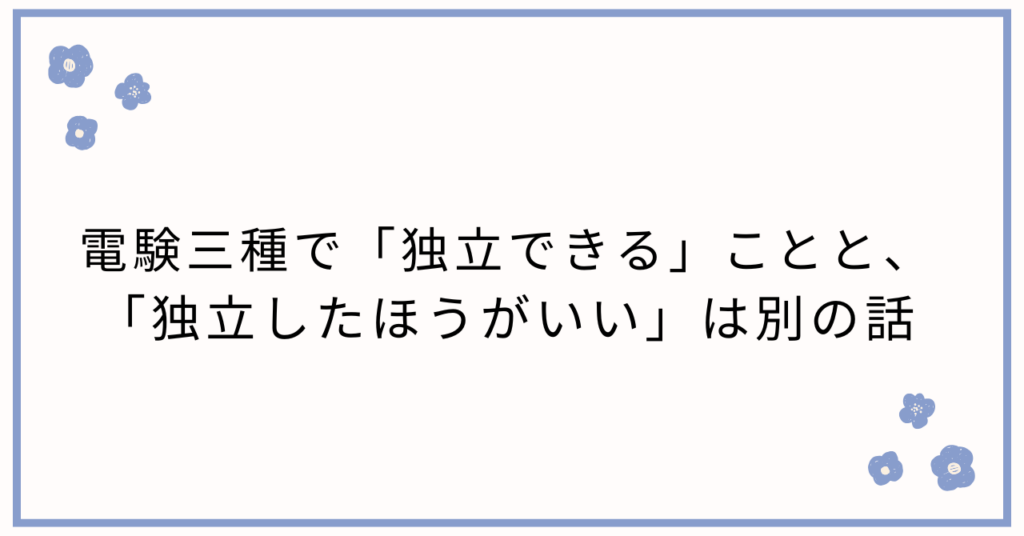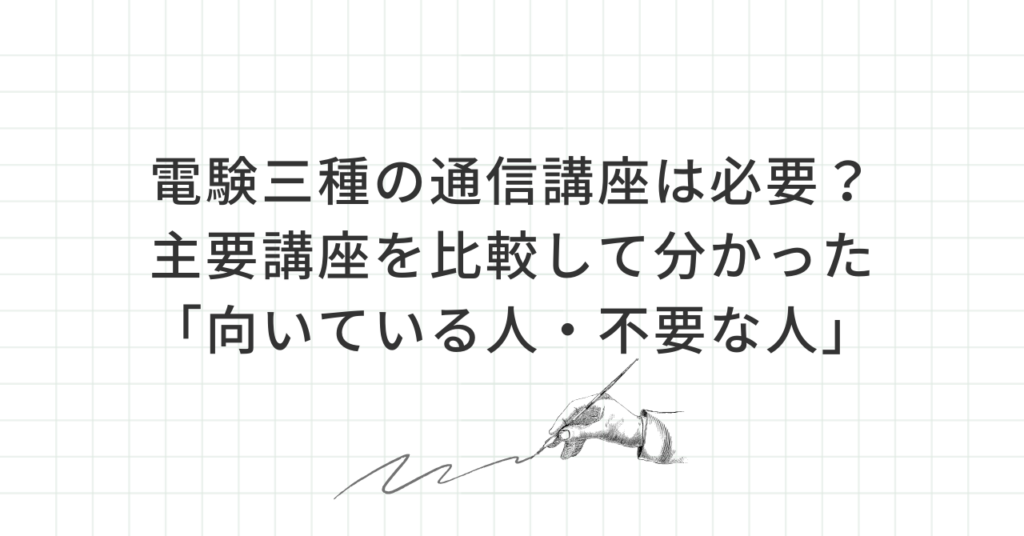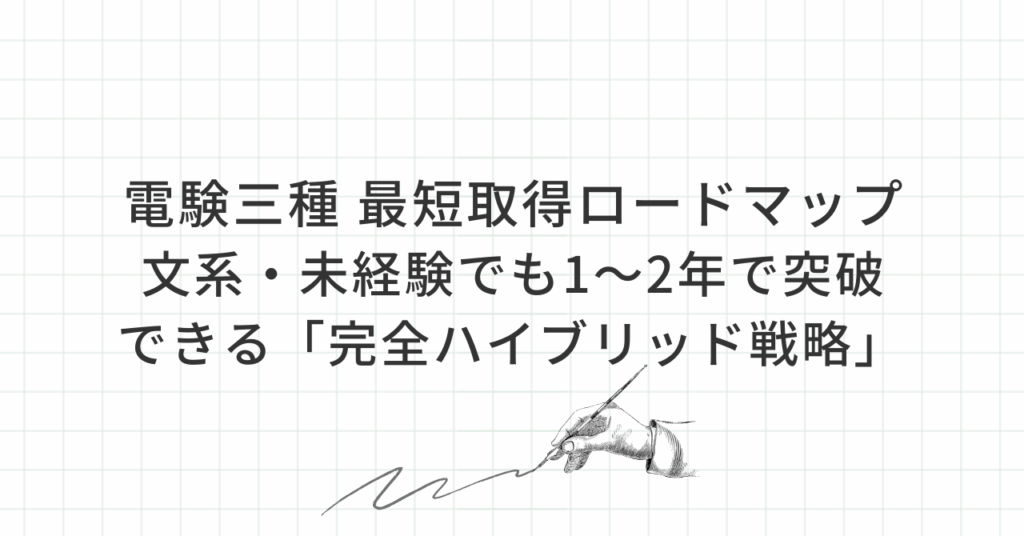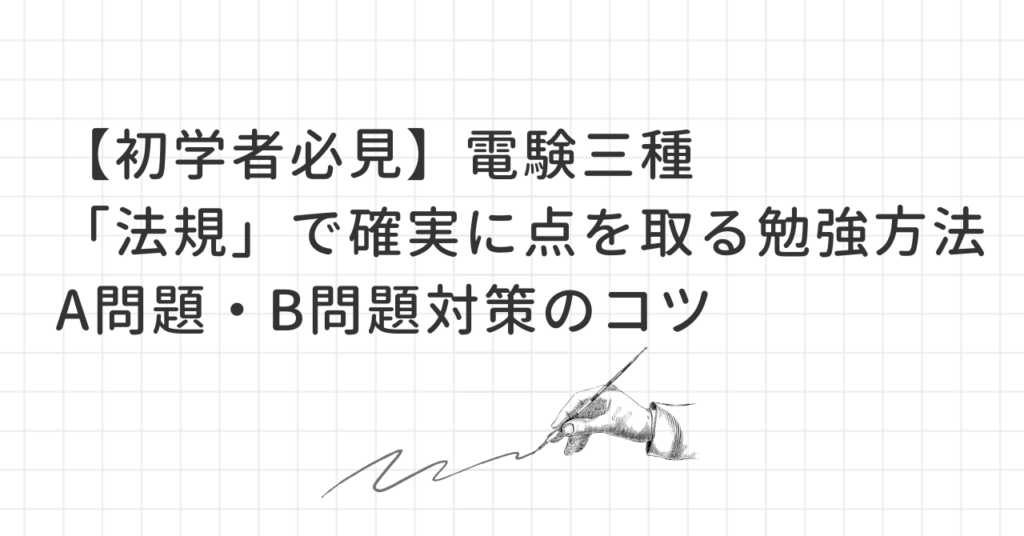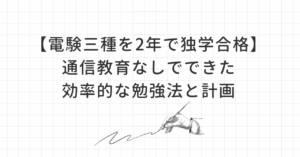Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。
電験三種(第三種電気主任技術者)は、電気系資格の登竜門として多くの社会人が挑戦する国家試験です。しかし範囲が広く、どこから手をつければいいか悩む人も多いのではないでしょうか。
私自身、最初は通信講座を利用しましたが、教材が分かりにくく、途中で挫折しました。その後、勉強方法を模索し、自分なりに改善することで4年間での独学学習で合格する事ができました。
その経験を経て、「独学で2年以内に合格する最短ルート」を自分なりに確立しました。
この記事では、その具体的な勉強法とスケジュールを紹介します。
電験三種は独学でも十分合格できる
まず結論から言うと、電験三種は独学で十分合格可能です。
市販の教材とネット上の学習リソース(YouTube・アプリなど)を活用すれば、
通信講座に頼らなくても合格レベルに到達できます。とくにCBT方式が導入されたことにより、過去問の焼き回しが増加したことでより受かりやすくなっています。たとえ、焼き回しがなくなっても、下記の通りにやれば、試験に合格するための理解力は得られると思います。
電験三種は出題傾向が安定しており、
「基礎理論+過去問理解」で合格点を取ることができます。
必要なのは、広く手を出すよりも“しっかりと”理解することです。
使用教材|「これだけシリーズ」で十分対応できる
独学に最適な教材は、オーム社の「これだけシリーズ」です。
この4冊で全科目をカバーできます。
イラストと図解が多く、専門書が苦手な人でも理解しやすい構成になっています。
他の参考書に手を出すより、このシリーズを使う方が良いと思います。私は完全マスターシリーズを最初に買って読みましたが、文字が小さく、分量が多いのがつらかったです。また完全マスターの機械は難しくて途中で挫折しました。『電験3種 これだけ機械』に関しては、youtubeで学習してから、テキストを読み込んだ方が効率的だと思います。
【『電験三種』でのおすすめ教材をこちらで紹介しています👇】

【1年目】理論・電力・法規を重点的に攻略する
1年目は「理論・電力・法規」の3科目に絞りましょう。
最初から4科目に手を出すと、学習の密度が下がり挫折しやすくなります。
手順①:全体像をつかむ
まずは「これだけシリーズ」を通読し、科目の構造を把握します。
理解できなくても構いません。1冊をとりあえず一読します。
手順②:YouTube講義で理解を深める
私は特に以下のチャンネルを活用しました。
- Aki塾長_電験三種チャンネル(特におすすめ)
- 資格とっ太郎チャンネル
これらの動画は解説が非常に丁寧で、
専門用語の意味や計算の流れを“言葉で理解”できます。
重要な部分はスクリーンショットを撮って、スキマ時間に見返して学習していました。それを講義内容が頭の中で再現できるまで繰り返し、人に教えられるレベルまで繰り返しました。
手順③:半年後に一度試験を受ける
一通り勉強したら、まず1年目の終盤で本試験を受けてみてください。
目標は合格ではなく、出題傾向と実力の把握です。
法規と電力は比較的早く得点できるので、1〜2科目の合格を狙いましょう。もし科目合格していたら機械に取り組んで良いと思います。
【2年目】理論を仕上げ、機械に合格する
2年目は「理論の完成」と「機械の攻略」に集中します。
特に理論は電験三種の“核”となる科目で、ここを理解できると他の科目の理解度も一気に上がります。
理論は過去問15〜20年分を解く
過去問の焼き直しが多い試験なので、過去問を深く理解することが最重要です(焼き回しはそのうちなくなるかもしれませんが)。
単に答えを覚えるのではなく、「なぜその選択肢が正しいのか」を説明できるまで落とし込みましょう。
理論を繰り返すうちに、計算パターンと問題傾向が体に染み込みます。
私は理論の不合格が続いているときに、「資格とっ太郎」さんのECM2.0講義を部分的に受講しました。そして、理論をより深く理解できるようになり、95点で合格しました(それまでの最高は55点で不合格でした)。
【『電験三種』でのおすすめ教材をこちらで紹介しています👇】

機械は動画+図解で克服
機械分野は電験三種の中でも挫折率が高い科目です。
しかし、YouTube講義と図解テキストを組み合わせれば独学でも十分対応可能です。
YouTube講義では、変圧器・同期機・電動機・発電機等のイメージがつかめるようになります。
理解できれば一気に得点源になります。
効率を上げる3つのポイント
① 動画で理解、過去問で定着
テキストで「読む」だけでは限界があります。
動画で理解 → 過去問で定着、という流れが効率的だと思います。
同じ内容を別の媒体で学ぶことで、記憶の定着率も高まりますのでおすすめです。
② 過去問の“間違いノート”を作る
過去問を解いたあと、間違えた問題は必ずノートにまとめてください。
「なぜ間違えたか」「どの公式を忘れていたか」を書き出すことで、弱点が明確になります。
これを試験直前に見返すだけで、合格率が大きく上がります。
③ 法規はアプリでスキマ時間に暗記
法規は暗記要素が強い科目です。
私はスマホアプリ(電験三種 法規科目 暗記アプリ)を活用し、通勤中に条文を確認していました。
完璧に覚える必要はなく、「見たことがある」「薄っすらと記憶する」レベルで十分です。

勉強時間の目安|2年間で1,200時間
- 1年目:1日2時間×週5日 → 約500時間
- 2年目:1日2時間+休日集中学習 → 約700時間
合計1,200時間前後が目安です。
2年あれば社会人でも十分到達できます。
重要なのは「毎日少しでも継続する」こと。
1日休むと再開が大変になるため、短時間でも机に向かう習慣を持ちましょう。
よくある失敗パターンと回避法
- 教材を増やしすぎる
→「これだけシリーズ」と「過去問+動画」で十分。参考書沼に入らないこと。 - 理論を後回しにする
→全科目の基礎になるので最初に固めることが大切。 - 過去問を解くだけで満足する
→理解せずに回しても伸びません。なぜそうなるかを説明できるように。
まとめ|「狭く深く」が最短ルート
電験三種は範囲が広く難関ですが、戦略的に学べば独学でも十分合格可能です。
✅ 教材は「これだけシリーズ」で統一(ただし機械は不要かもしれません)
✅ 1年目は理論・電力・法規(科目合格すれば、すぐに機械を学習)、2年目は理論仕上げ+機械
✅ 過去問・動画・アプリで学習効率を最大化
✅ 広く浅くより「しっかり」理解する
この2年計画を着実に進めれば、働きながらでも合格できます。
焦らず一歩ずつ積み重ねることこそが、最短ルートです。
過去問に関して、20年分もやれば合格はかなり近くなります。
【『電験三種』でのおすすめ教材をこちらで紹介しています👇】

▼ note / X(Twitter)でも発信しています
\ 学習・キャリア戦略の最新情報はこちらでも発信中 /
- note(ストーリー・キャリア戦略):けんしろう ❘ 凡人のキャリア再構築
→ 再スタートを切りたい人向けの深い内容、書き下ろしの体験談を更新中。 - X(Twitter):けんしろう|凡人のキャリア再構築
→ 公務員試験・資格勉強の「毎日の気づき・短文Tips」、キャリアの考え方を発信。