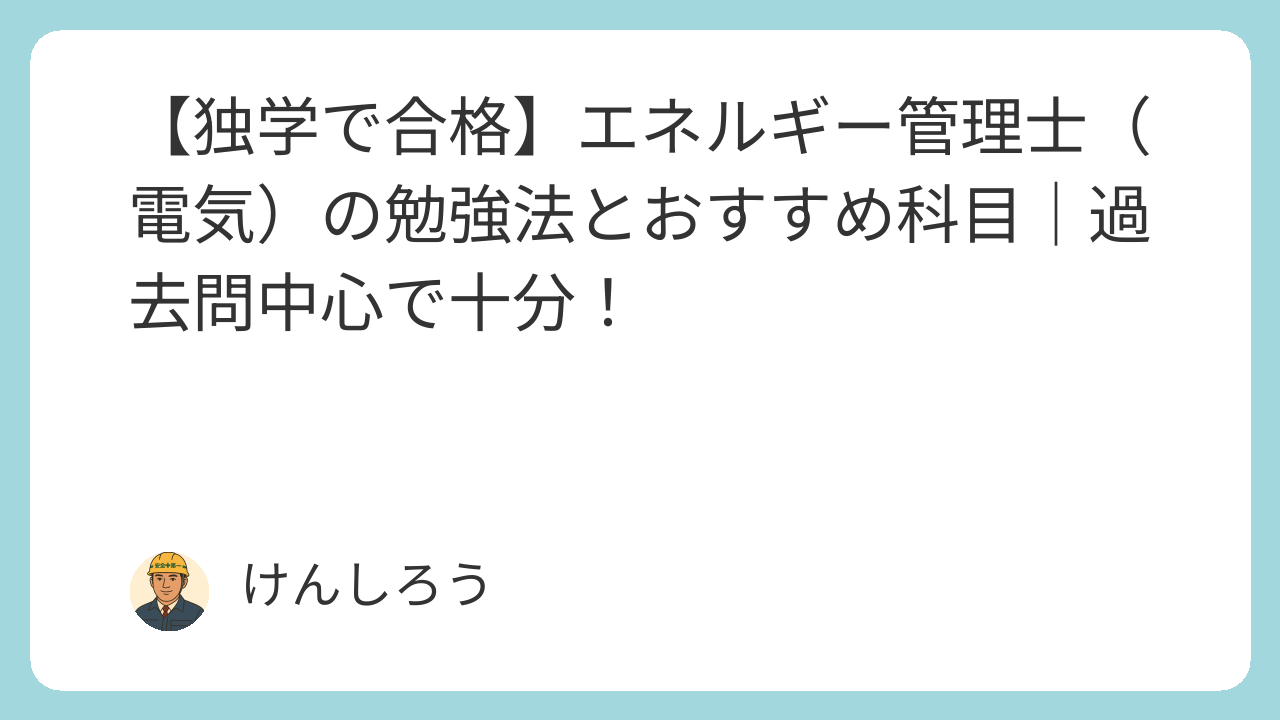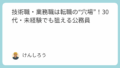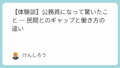「エネルギー管理士(電気)」は、電気技術者としてのキャリアを確実にステップアップできる国家資格です。
この記事では、私が独学で合格した勉強法を実体験ベースで解説します。
結論から言えば——この資格は過去問中心の勉強だけで十分合格可能です。
高額な通信講座や教材を使わなくても、電験三種に合格した方なら過去問をひたすら解くことで合格できます。
エネルギー管理士とは?難易度と位置づけ
エネルギー管理士は、工場・ビルなどで省エネルギー管理を行うための国家資格で、「エネルギーの効率利用促進法」に基づく専門職です。
電気と熱の2分野がありますが、「電気分野」に焦点を当てます。
難易度は「電験三種より少し上」と表現されますが、私はやや下だと考えます。
根拠として、問題が素直なことが多いからです。
ただし、これがあてはまるのは電験三種を持っている人もしくは同等の知識を有する人です。
試験範囲には共通する部分が多く、既に電験三種を学んでいる人なら知識をそのまま活かせます。
「電験三種の延長戦」として考えるとイメージしやすいでしょう。
使用教材はこれ1冊でOK!過去問中心で十分対応できる
私が使用した教材は、市販の過去問題集だけです。
具体的には次の書籍を使用しました。
📘 『エネルギー管理士 電気分野 過去問題集』(オーム社)
この試験は、出題傾向が毎年ほぼ同じです。
そのため、過去10年分を繰り返すだけで出題パターンを完全に把握できます。
特にオーム社の過去問集は解説が丁寧で、問題ごとに重要ポイントが整理されています。
通信講座に数万円を払うよりも、過去問+ネット検索のほうがコスパが圧倒的に良いです。
数学レベルは中学〜高校程度|微積分はYouTubeで補える
「微分や積分が出る」と聞くと構えてしまう人も多いかもしれませんが、実際は高校レベルの基礎数学で十分です。
私は電験三種の勉強で基礎を理解していたため、
必要なときだけYouTubeで「微分 積分 基礎」「エネルギー管理士 微積分」などと検索して学びました。試験で問われる微分積分は簡単な基本公式を覚えれば対応できます。
YouTubeでは無料で分かりやすい講義動画が多数あり、
「わからない→調べる→過去問で確認」の繰り返しで自然と理解が深まります。
ポイントは、“わからないまま放置しない”こと。
難しい理論も、動画や図で視覚的に理解すれば一気に進みます。
勉強方法|過去問を“理解して”回すのが最短ルート
私が実践した独学法はとてもシンプルです。
- 過去問を1年分解く
- わからない問題を調べる(ネットや電験テキストで補う)
- 理解したらもう一度解く
- 間違えた問題、苦手な部分をノートに整理する
これを繰り返すだけです。
単に「暗記」するのではなく、“なぜそうなるのか”を説明できる状態にしておくことが大切です。
誰かに解法を説明できるほどであれば、テストで得点をすることは難しくはないと思います。
過去問を「理解して回す」ことこそ、最も効率的な勉強法です。
10年分を3周すれば、出題パターンがほぼ見えてきます。それが終わった後も試験までは繰り返す。
勉強時間の目安|電験三種合格者なら300〜600時間
勉強時間は人によって差がありますが、目安として次の通りです。
- 電験三種合格者:300〜600時間
- 未経験からの挑戦:800〜1,000時間程度
1日2〜3時間を確保できれば、半年〜1年で合格可能です。
社会人なら、通勤時間や昼休みをうまく活用すると勉強が続けやすくなります。
私は夜1時間+休日3時間ペースで学習を進めました。
私は2回で合格しました。
ですので総勉強時間は550時間です(1年目に3科目。2年目に1科目)。
選択科目のおすすめ|「電気加熱」と「照明」で得点源を作る
エネルギー管理士(電気)試験では、4つの選択科目から2科目を選びます。
私のおすすめは以下の3科目です。
- 電気加熱
- 照明
- 電気化学
- 空気調和
この中でも特におすすめは「電気加熱」と「照明」。
理由はシンプルで、公式暗記で解ける問題が多く、安定して得点できるからです。
「電気加熱」は暗記要素が強く、出題パターンがほぼ固定されています。
「照明」も出題形式が似ており、電験三種の知識がそのまま使える部分も多いです。
逆に「電気化学」は少し難易度が高いように感じました。電験三種では空気調和は学習していませんので、得意でなければ避けた方が良いと思います。
モチベーション維持のコツ|“ゴールを細かく設定する”
独学の最大の敵は「継続の難しさ」です。
エネルギー管理士は長丁場の試験なので、モチベーション維持がカギになります。
私が意識していたのは、小さなゴールを設定すること。
「今週は分野Aを終わらせる」「3日で過去問1年分」など、
細かく区切ることで達成感を得やすくなります。
また、勉強記録アプリ(Studyplusなど)を使って進捗を可視化するのも効果的です。これによりどの科目に時間を割いているのかも客観的に分かるのでおすすめです。
見える化することで、自然と習慣化することもできます。
試験直前期の対策|“捨て問”を決めて時間配分を最適化
直前期はすべての問題を解こうとせず、捨てる勇気を持つことも重要です。
試験時間は限られているため、「難問は後回し」にする冷静さが合否を分けます。
特に計算量の多い問題は、時間を食われやすいので、
「取れる問題から確実に得点する」戦略で挑むのがおすすめです。
また、試験本番では途中計算をきれいに書いておくこと。
ミスを減らし、見直し時にすぐ修正できます。問題用紙に自分の書いた計算式を分かりやすくしておけば、あとで見直し時に楽になります。
合格後に感じたこと|実務とつながる“使える資格”
エネルギー管理士が正直、評価をされるのか、役に立つのかは分かりません。
私は筆記試験で取得しましたが、講習で取れる環境があるのなら講習での取得を勧めます。少ない労力で同じ結果が得られるのであれば、楽な方を選んだ方が良いです。
たとえ、認定や講習での取得であろうとも、電気主任技術者やエネルギー管理士を持っていると将来的には役に立つと思います。
また法的にも一定規模以上の事業所ではエネルギー管理士の配置が義務づけられており、需要が安定している点も魅力です。
まとめ|過去問を理解して回せば独学でも合格できる!
エネルギー管理士(電気)は、一見難関に見えますが、
過去問を理解して繰り返すだけで十分に独学合格が可能です。
✅ テキスト不要、過去問中心でOK
✅ 電験の知識を再利用して効率化
✅ 選択科目は「電気加熱」「照明」がおすすめ
「電験三種に合格したけど、次の目標を探している」
「省エネ分野でキャリアを伸ばしたい」
そんな方にとって、エネルギー管理士は最適なステップアップ資格です。
正しい方法で学べば、独学でも十分にチャンスがあります。
独学でも十分に合格可能ですが、講習で取得できる機会があれば、講習での取得を勧めます。